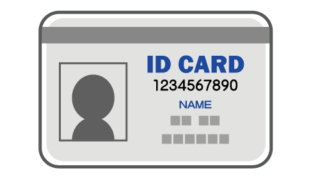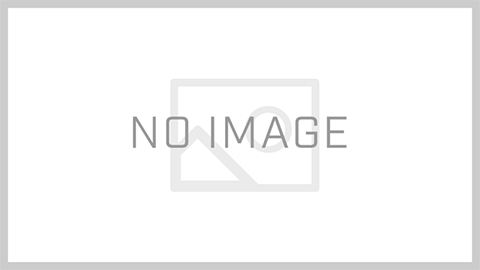1.有訴者について
2019年の国民生活基礎調査によると、有訴者率は人口千人当たり 302.5となっている(選択肢の値は、65歳以上の割合)。また、性別にみると、男 270.8、女 332.1 で女が高いことがわかる。症状別にみると、男性では「腰痛」での有訴者率が最も高く、次いで「肩こり」、「鼻がつまる ・鼻汁が出る」。女性では「肩こり」が最も高く、次いで「腰痛」、「手足の関節が痛む」となっ ている。選択肢の「頭痛」は、5番目に多い。
2.有病率と罹患率について
有病率とは、ある一時点において、疾病を有している人の割合のことであり、罹患率とは、一定期間にどれだけの疾病(健康障害)者が発生したかを示す指標のことである。追跡期間中に対象者が観察集団から脱落したりすることで追跡バイアスが生じるため、罹患率の分母には、観察された対象者と各対象者についての観察期間を同時に考慮に入れて、人年法が用いられている。年の途中で転入・転出、罹患・死亡が発生した場合は0.5人年、同一年内に転入・転出、罹患・死亡が発生した場合は0.25人年として計算する。また、罹患率と有病率との間には、平均有病期間がほぼ一定であるとき比例の関係が成り立っている。(日本疫学会のサイトより引用)
3.受診率について
全国の受療率(人口10万対)は、「入院」1,036、「外来」5,675である。
性別にみると、入院・外来ともに、女性が高く、入院では「男」972、「女」1,096、外来では「男」4,953、「女」6,360となっており、年齢階級別にみると、入院、外来ともに「65歳以上」が最も高くなっているが、年次推移では減少傾向となっている。
※65歳以上をさらに細かく分けた場合、入院の場合は、年齢が上がるにつれて、割合も高くなるのに対し、外来では、80~84歳がピークであることに注意。
傷病分類別にみると、入院では、高い順に「Ⅴ精神及び行動の障害」199、「Ⅸ循環器系の疾患」180、「Ⅱ新生物<腫瘍>」112となっている。外来では、「ⅩⅠ消化器系の疾患」1,021、「Ⅸ循環器系の疾患」702、「ⅩⅢ筋骨格系及び結合組織の疾患」692となっている。
4.平均在院日数について
平均在院日数を施設の種類別にみると、「病院」30.6日、「一般診療所」12.9日となっており、病院、診療所ともに減少傾向となっている。
年齢階級別にみると、年齢階級が上がるに従い退院患者の平均在院日数は長くなる傾向がある。傷病分類別にみると、長い順に「精神及び行動の障害」277.1日、「神経系の疾患」81.2日、「循環器系の疾患」38.1日となっている。病床別にみた在院機関の割合では、病院全体の68.2%が「0~14日」となっているが、精神病床だけでは、「1~3月未満」が39.2%で最も多く、感染症病床では、「0~14日」が87.0%で最も多く、結核病床では、「1~3月未満」が47.4%で最も多く、療養病床では、「1~3月未満」が40.4%で最も多い。
5.外来の受療行動(2017)について
この病院を選んだ理由があると回答した者について、選んだ理由をみると、外来・入院ともに「医師による紹介」が最も高く、外来で38.1%、入院で 51.6%、次いで、外来では「交通の便がよい」が27.2%、入院では「専門性が高い医療を提供している」が25.7%となっている。
外来患者の来院の目的をみると、「診察・治療・検査などを受ける」は、89.9%、「健康診断(人間ドックを含む)・予防接種」は3.9%となっている。来院の目的が「診察・治療・検査などを受ける」者について、診察・治療・検査などの内容をみると「定期的な診察と薬の処方を受ける」が40.9%と最も多く、次いで「症状を診てもらう」が24.2%、「検査を受ける、または検査結果を聞く」が17.2%となっている。
外来患者が受診した病気や症状を初めて医師に診てもらった時、「自覚症状があった」は68.0%、「自覚症状がなかった」は25.8%となっている。「自覚症状がなかった」と回答した者の受診した理由をみると、「健康診断(人間ドックを含む)で指摘された」が42.7%と最も高く、次いで、「他の医療機関等で受診を勧められた」が23.0%となっている。
受診までの期間が「1週間以上」の者について、自覚症状の有無別に受診までに時間がかかった理由をみると、「自覚症状があった」では「まず様子をみようと思った」が63.5%と最も高く、「自覚症状がなかった」では「医療機関に行く時間の都合がつかなかった」が30.9%と最も高くなっている。
(2017年度患者調査より引用)