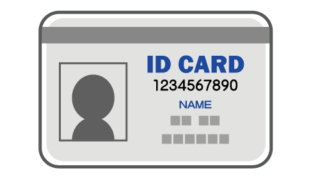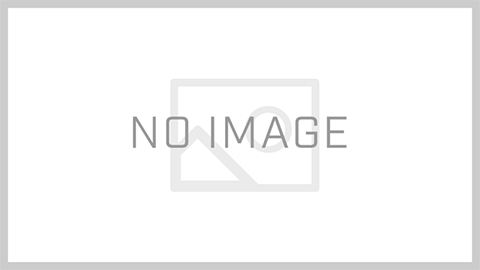1.医療保険について
公的医療保険は会社などに勤めている人が加入する「被用者保険」、個人事業主や非正規雇用者、会社を退職した人などが加入する「国民健康保険」、75歳以上を全員対象とする「後期高齢者医療制度」の大きく3つに分けることができる。
被用者保険の中でも、大企業を対象とした「健康保険組合」、中小企業を対象とした「協会けんぽ(全国健康保険協会)」、公務員を対象とした「共済組合」に分けられている。
窓口での負担割合は、原則3割負担ではあるが、自治体や所得、年齢によって異なっており、小学校入学までは「2割」、小学校入学後から69歳までは「3割」、70歳から74歳までは「2割」、75歳以上は「1割」となっている。ただし、70歳以上でも、現役並みの所得がある場合は、「3割」負担となる。
2.国民皆保険制度について
わが国では、1961年に国民皆保険制度が成立することで、「誰も」が「いつ」「どこにいても」保険証があれば、同じ医療を受けることができるようになっている(保険診療)。一方で、保険の適応のない「自由診療」の在り方について議論されている。公的な医療保険への加入義務を有するが、生活保護受給者は、医療保険には加入できず、医療扶助(現物支給)を受ける点は、例外として注意しておく。
3.国民医療費について
平成29年度の国民医療費は43兆710億円、前年度の42兆1,381億円に比べ9,329億円、2.2%の増加となっている。人口一人当たりの国民医療費は33万9,900円、前年度の33万2,000円に比べ7,900円、2.4%の増加となっている。国民医療費の国内総生産(GDP)に対する比率は7.87%(前年度7.85%)、国民所得(NI)に対する比率は10.66%(同10.77%)となっている。
また、年齢別に人口一人当たり国民医療費をみると、65歳未満は18万7,000円、65歳以上は73万8,300円となっており、性別に人口一人当たり国民医療費をみると、65歳未満の男は18万8,600円、女は18万5,400円、65歳以上の男は79万4,700円、女は69万4,900円となっている。(男性だけなら、33万8,600円、女性だけなら、34万1,200円で平均的)
4.後期高齢者医療制度について
被保険者は、75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で重度の障害をもつと認められた者となっている。運営主体は、都道府県単位ですべての市町村が参加してつくられる後期高齢者医療広域連合である。保険料は、特別領収であり、年金からの天引きによって徴収されている。後期高齢者が医療を受けた場合の自己負担は、原則1割負担であるが、一定の所得がある者は、3割負担となっている。
5.社会保障給付費
社会保障(88%):医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険
社会福祉(8%):児童福祉、身体障害者福祉、高齢者福祉
公的扶助(3%):生活保護
公衆衛生(1%):感染予防、予防接種