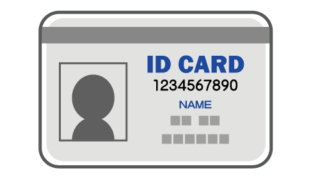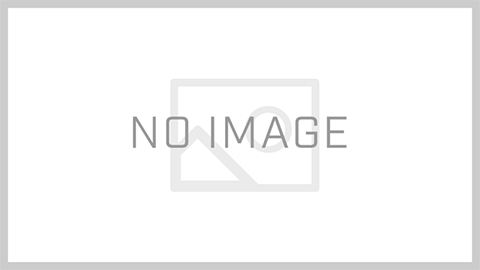1.倫理原則について
自律尊重の原則とは、患者が自己決定するために必要な情報を提供し、そのうえで患者が決定した内容を尊重し、従うこと。
善行の原則とは、患者の考える最善の利益を得られるために努めること。医療者が考える患者にとっての利益ではなく、患者が考える最善の利益。
無危害の原則とは、患者に危害を与えないこと。また、患者に身体的・精神的・社会的な危害が生じるリスクを回避すること。
公正と正義の原則とは、全ての患者に対し、患者のニーズに従って、適正かつ公平なヘルスケア資源の配分を行うこと。
誠実と忠誠の原則とは、患者に対し正直であること。また、患者と看護師の間の信頼関係に内在する義務に対して誠実であること。
2.看護師に求められる役割について
アカウンタビリティとは、説明責任のこと。看護師には、患者に対して行われる治療や処置に関する内容を、患者や家族へ説明する責任がある。
アドボカシーとは、権利擁護のこと。患者が自身の権利を守るための自己決定をできるように支援すること。代弁者ともいわれる。
エンパワメントとは、患者が持つ力(生きる力や健康促進への力)を看護師が湧き出させるよう援助すること。
3.自己決定について
インフォームドコンセントとは、「患者は、医師等から診療内容などについて十分な説明を受け、十分に理解した上で、患者自身が同意の上で、最終的な診療方法を選択すること」です。
ヘルスプロモーションとは、「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」のことです。
リビングウィルとは、「人生の最終段階(終末期)を迎えたときの医療の選択について事前に意思表示しておく文書」のことです。
プライマリ・ヘルス・ケアとは、「すべての人にとって健康を、基本的な人権として認め、その達成の過程において、住民の主体的な参加や自己決定権を保障する理念」
ノーマライゼーションとは、「障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す」ことを指します。
4.保健師助産師看護師法について
第二条(保健師の定義):この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
第三条(助産師の定義):この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第五条(看護師の定義):この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第六条(准看護師の定義):この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第十五条の二(保健師等再教育研修):厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師若しくは看護師又は同条第三項の規定により保健師、助産師若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師若しくは看護師としての倫理の保持又は保健師、助産師若しくは看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。都道府県知事は、第十四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。
第二十八条の二(保健師、助産師、看護師及び准看護師の研修):保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第二十九条(保健師業務の制限):保健師でない者は、保健師又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。
第三十条(助産師業務の制限):助産師でない者は、第三条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第三十一条(看護師業務の制限):看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第三十二条(准看護師業務の制限):准看護師でない者は、第六条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第三十三条(氏名、住所等の届出義務):業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第四十二条 2(助産録の記載及び保存):前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。※看護記録は、二年間(医療法)。
第四十二条の二(秘密保持義務):保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。※助産師は、刑法。
5.看護師等人材確保促進法について
この法律の下、今後必要となる看護職員を着実に確保するために、「養成促進」「復職支援」「離職防止・定着促進」「財政支援」に取り組んでいる。看護師等免許保持者の届出制度は、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方を対象としており、復職に備えた支援を行うものである。2年ごとに提出義務のある業務従事者届は、保健師助産師看護師法に規定された制度であり、どの地域にどれぐらいの医療従事者がいるのかを把握するための情報として用いられている。
ナースセンターは、復職を考えている看護師に対し、求人情報を提供するための機関であり、看護協会の指定を受け、都道府県単位で設置されている。同じ求人情報を扱うハローワークとの連携強化が求められている。
この法律では、看護師のみならず、社会人経験者で看護師学校養成所を目指す方を対象とした単位認定や経済支援も行っている。