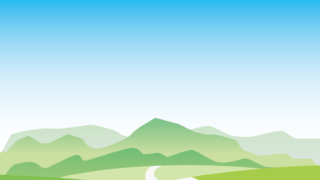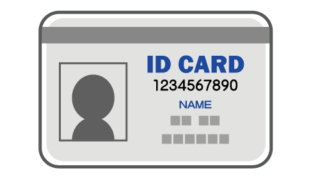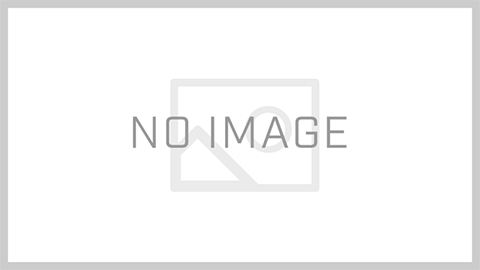1.Japan Coma Scaleについて
| Ⅰ | 刺激しないでも覚醒している状態 |
| 0 | 意識清明 |
| Ⅰ-1 | だいたい清明であるが、今ひとつはっきりしない |
| Ⅰ-2 | 見当識障害がある(場所や時間、日付が分からない) |
| Ⅰ-3 | 自分の名前、生年月日が言えない |
| Ⅱ | 刺激で覚醒するが、刺激をやめると眠り込む状態 |
| Ⅱ-10 | 普通の呼びかけで容易に開眼する |
| Ⅱ-20 | 大きな声または体を揺さぶることにより開眼する |
| Ⅱ-30 | 痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すことにより開眼する |
| Ⅲ | 刺激しても覚醒しない状態 |
| Ⅲ-100 | 痛み刺激に対し、払いのける動作をする |
| Ⅲ-200 | 痛み刺激に対し、少し手足を動かしたり、顔をしかめたりする |
| Ⅲ-300 | 痛み刺激に反応しない |
2.呼吸音聴取
| ラ音 | 名称 | 英語名 | 聞こえ方 | 代表疾患 |
| 断続性 | 水泡音 | coarse crackle | プツプツ | 肺炎、肺水腫 |
| 断続性 | 捻髪音 | fine crackle | バリバリ | 間質性肺炎 |
| 連続性 | 笛音 | wheeze | ヒューヒュー | 気管支喘息 |
| 連続性 | いびき音 | rhonchi | グーグー | 気道閉鎖 |
「ラ音」とは、雑音のことです。聞こえ方が、プツプツと断続的なのか、ヒューヒューと連続しているのかで分類しています。
断続性は、肺が膨らみにくくなっていて、頑張って膨らもうとしている状態(風船にテープを張って膨らますと、バッバッとなる感じ)をイメージしましょう。
連続性は、気道が狭くなっていて、笛みたいにヒューって風が通る状態(口笛の時、口をすぼめる感じ)をイメージしましょう。
3.腹部蠕動音聴取
腸蠕動音は、音の大きさよりも、回数で評価されます。
「正常」・・・5~15回/分
「減少」・・・1回もない/分
「消失」・・・1回もない/5分
「亢進」・・・35回以上/分
もちろんですが、「亢進」していれば、大きく聞こえがちで、「減少」していれば、小さく聞こえがちですが、その時の状況や個人差があります。
4.運動機能の評価
ROM訓練は、関節可動域に異常がないかを、患者自身が動かしたり(自動運動)、医療者側が動かしたり(他動運動)することで、評価します。
範囲広いので、ここでは割愛します(ゴメン💦)が、自身の関節の動きと合わせて覚えるとわかりやすいと思います。
また、「内旋と外旋」「内転と外転」「回内と回外」といった名前の似ているものは、問われやすいので、しっかりと確認しておきましょう。
MMTは、徒手筋力テストのことで、筋力の低下の程度を6段階で評価します。一般的に、日常生活を営むためには、3以上の評価があると良いと言われています。
| 5 | Mormal | 強い抵抗を加えても、関節運動あり。 |
| 4 | Good | 抵抗を加えても、関節運動あり。 |
| 3 | Fair | 重力があっても、関節運動あり。 |
| 2 | Poor | 重力がなければ、関節運動あり。 |
| 1 | Trace | 筋収縮あるが、関節運動はない。 |
| 0 | Zero | 筋収縮なし |
通常に生活するうえで、重力は必ずかかりますので、「3」が基準です。常に、重力以外の抵抗が働いている人がいれば、「4」以上は欲しいですね。
5.バイタルサイン測定
血圧を測る前は、安静でいる必要があります。たとえ減塩食であろうが、有酸素運動をしていようが、長い目で見れば、血圧への影響としては良いかもしれませんが、その測定時点で見た場合、食事をとるという行為による血圧の変動が見られてしまいます。
成人で、目立った心疾患等なければ、左右差はあまり見られませんが、心臓からの位置や血管の太さによって、血圧の値が変わりますので、気をつけましょう。一般的に、収縮期血圧が80mmHgを超えていれば、橈骨動脈での触知が可能ですが、それ以下では、触れなくなってしまいます。
血圧計のマンシェットをまく際に、2本分の指が入るように緩めるのは、巻いたときに生じる圧を減らすためであり、聴診器を差し込むためではありません。また、マンシェットの位置と、心臓との位置に高低差があれば、血圧の値も変動しますので、注意が必要です。