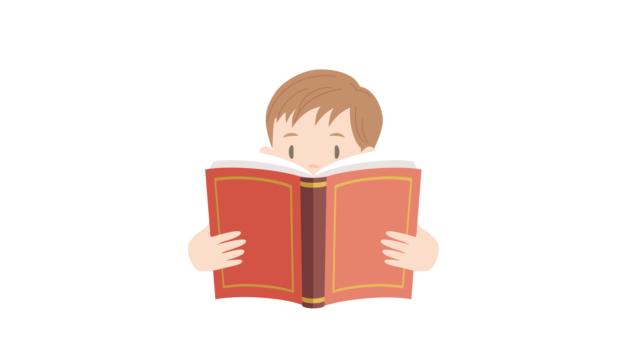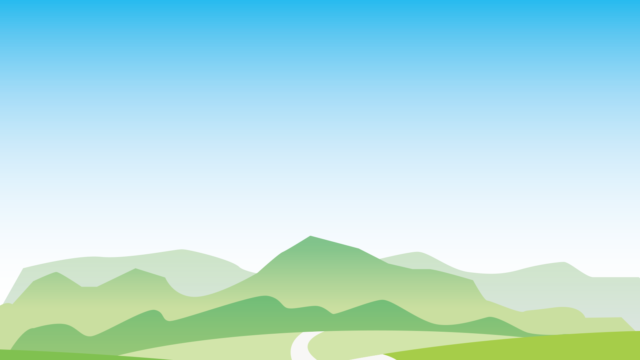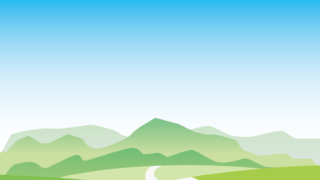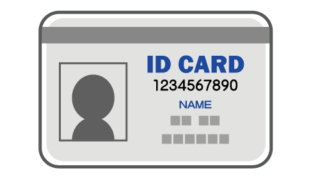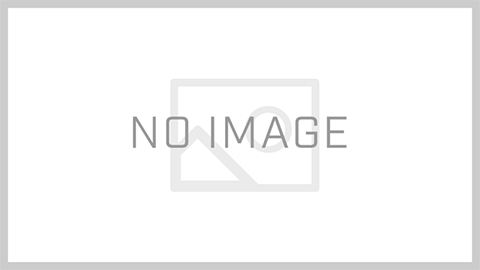こんにちは、soraです。
やっとここまでたどりつきましたね。今回の看護計画は、アセスメントとならんで、みんなを悩ませる箇所であると思います。頑張っていきましょう。
看護計画は、観察項目(O-P)、治療計画(T-P)、教育計画(E-P)にわかれます。観察項目は、初めに書きがちですが、最後にしたほうがわかりやすいので、治療計画から進めていきます。
この項目では、看護師として、患者さんに「やること」を書いていきます。
「〇〇する」とか「~実施する」あたりの語尾になることが多いと思います。
この項目では、看護師として、患者さんに「伝えること」を書いていきます。
「〇〇を説明する」とか「△△を指導する」とか「~を伝える」あたりの語尾になることが多いと思います。
これら2つの項目では、特に具体性と個別性が求められます。
具体性:その計画を他の看護師が見ても実施できること。
個別性:その患者さんのみが使えるオリジナル計画。
看護師は、24時間ずーっと患者さんのことを看ておかなければなりませんが、一人の看護師でそれを行うのは不可能です。そのため、具体的な看護計画を立て、他の看護師にも同じ質の看護が提供できるようにしています。
また、同じ転倒リスクに関わるとしても、患者さんが異なれば、説明する方法や実際の関わり方が変わってきます。それが個別性です。
まずは、該当する看護診断の標準看護計画を書いてみましょう。その上で、具体性や個別性を考えていく方が、速く仕上げるための近道です。
プランを書いた後で、一度その計画が本当に適切かどうが見直してみましょう。
一般的には、必要なことでも、その患者さんには当てはまらないことがよくあります。
この項目では、T-PやE-Pで実施したケアで、患者さんがどう影響したかを観察していきます。
例えば、清潔ケアを行ったのであれば、それによって、皮膚の状態がどうか、患者さんの反応はどうかを見ていく必要があります。また、教育や指導を行ったのであれば、患者さんが理解したのか等みていく必要があります。
立案したケアのすべてが評価できるように、観察項目を追加していきましょう。
それに合わせて、目標や診断指標についても評価していく必要がありますので、観察項目に追加していきます。
看護計画でよく問題となるのは、バイタルサイン測定を入れるのかどうか、またどの位置に入れるのかだと思います。
何かしらの介入を行う場合、そこには、脈拍や血圧等の変動は伴いますか?
リハビリを行う場合、前後でバイタルサインを測定すると思います。また、精神面への介入をする際、患者さんが緊張から過呼吸になることもあるかもしれません。
そのような場合、あなたは、バイタルサインを見ていることだと思います。
何をするにしても、患者さんの循環動態から得られる情報は大切なことが多いので、書いておくことが無難です。
上記の場合では、あくまでO-Pとしての関わりであることは、お分かりだと思いますが、例えば、術後管理で、バイタルサイン測定の位置づけのウエイトが大きい場合、T-Pとして考えることもあります。
8講時目.「O-P、T-P、E-P」の考え方と書き方。